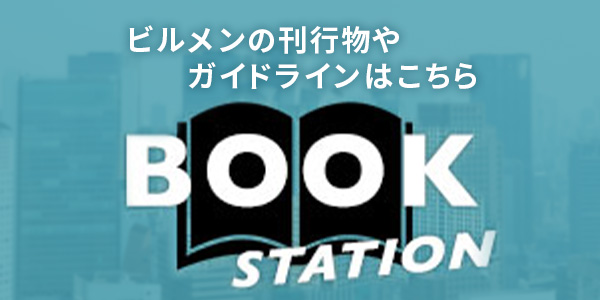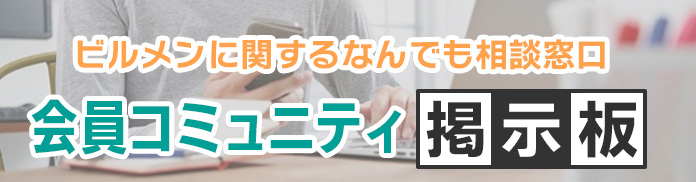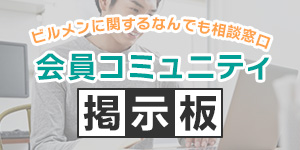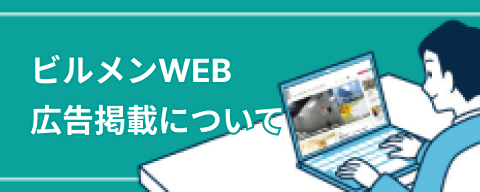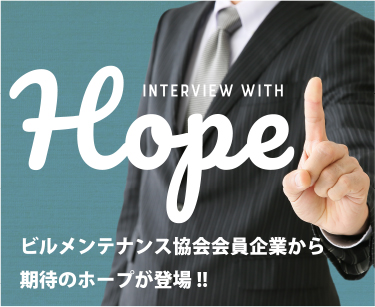
持続可能な組織をつくる—―人・技術・多様性の力で未来をひらく
FILE 087
昌永産業 株式会社
代表取締役社長 金井 晃海 氏

―――どのようなお子さんでしたか?
金井 小学校3年生から高校卒業まで、「海洋少年団」という海に関する活動を行う団体に所属していました。これはボーイスカウトのような団体で、主にカッター(手こぎボート)競技や手旗信号など、海に関する訓練や大会に向けた活動を行っていました。
小学生の頃は正直あまり乗り気ではなく、参加するのが億劫な時期もありました。しかし、中学・高校と進むにつれて全国大会を目指す競技の中心メンバーとなり、「自分が頑張らなければ」という責任感が芽生え、次第にやりがいを感じるようになりました。仲間と一緒に取り組むことも楽しくなり、自然と前向きに活動に参加できるようになっていったと思います。
高校卒業後も大学に通いながら、2〜3年ほど指導者として後輩の指導に携わりました。活動は基本的に土日中心で、中学・高校時代はほぼ毎週参加していた記憶があります。
また、学校では中学時代に柔道部、高校ではラグビー部に所属し、体を動かすことが好きで、さまざまな形で積極的に外に出て活動していました。
―――御社は小田原ラグビー協会の賛助会員もされていますね。高校時代にラグビー部だった影響ですか?
金井 正直なところ、「もう二度と関わるものか」と思っていたくらい、ラグビーに対しては否定的な気持ちを持っていました。学生時代にラグビー部に所属していたこともありましたが、それでも「こんなスポーツ」とすら思っていたほどです。
しかし、2019年にラグビーワールドカップが日本で開催されると知って、気持ちに少し変化がありました。
それまでラグビーには観客も少なく、寒々しい雰囲気という印象を持っていたため、「世界中からお客さんが来るのに、スタンドがガラガラだったら恥ずかしいな」と思い、何試合か観に行こうとチケットを取り始めたのです。
結果的には、そんな心配はまったくの杞憂でした。スタジアムは連日大盛況で、あの熱気と一体感に触れているうちに、自然と「もう少し見てみようかな」という気持ちになっていきました。
その後も国内リーグ「リーグワン」がスタートし、コロナ禍を挟みつつも、屋外での開催という安心感もあって、試合を観に行く機会が増えていきました。
そんな中、地元で親しくしている方が、たまたまラグビー協会の理事のような立場にあることを知り、「じゃあ、少しだけでもお手伝いしましょうか」と、ごく自然な流れで関わるようになりました。
気づけば、かつてあれほど距離を置こうとしていたラグビーに、再び関わる自分がいたのです。
―――大学卒業後に現在の昌永産業に入社されたんですか?
金井 ゆくゆくは昌永産業の三代目として働くことを視野に入れていましたが、大学では海洋学部・海洋土木工学科を専攻し、「まずは現場を知るべきだ」と考えて、海に関わる土木会社で現場監督として勤務しました。
ただ、長く勤めたわけではありません。いわゆる“業界あるある”かもしれませんが、非常に厳しい労働環境で、いわゆるブラックな側面もありました。
その頃から謎の微熱や咳が続くようになり、両親に相談したところ、「そろそろ昌永産業で働くのもいい時期では」となり、入社を決めました。
今振り返ると、人生の転機というのは本当に突然やってくるものだと感じています。

―――昌永産業に入社後はどのような仕事をされたんですか?
金井 入社して最初の2年間は、薬品製造現場で製造補助としての業務に携わっていました。派遣のような形で各製造棟に入り、製品の袋詰め作業や原料の運搬、清掃、工程準備など、日々異なる業務を担当していました。
製造スパンが長い現場だったため、「今日は倉庫から原料を運ぶ」「明日は袋詰め」「工程が終わったら部屋を洗浄し、次の準備に入る」といったように、仕事内容は日ごとに変化し、柔軟な対応力が求められる環境でした。
私は8〜10名ほどのチームの一員として現場に入り、作業員として勤務していました。もちろん、自分がいずれ経営層として関わる立場であることは周囲も理解していましたが、現場ではあくまで一作業員として、他のメンバーと同じ目線で業務に取り組むことを心がけていました。
その後、小田原に来てからは、クリーンルーム内の清掃業務を中心に、防虫・防鼠管理や製造現場での環境モニタリングなど、非常に多岐にわたる業務に携わってきました。
―――御社は幅広い業務をされているんですね?
金井 はい、業務の範囲は非常に柔軟で、「人手が足りないから薬品を詰める箱をひたすら折ってほしい」といった依頼を受けることもありますそのような作業が必要になった際には、対応可能なメンバーで現場に入り、サポートしています。
私たちの会社の特徴は、いわゆる「清掃業」や「ビルメンテナンス」といった枠にとらわれず、工場や現場で発生する“困りごと”全般に対応している点です。工場にはもちろん、電気・配管・機械・建設などの専門業者もいますが、その間(はざま)にあるような、「誰がやるか決まっていないけれど、誰かがやらなければならない仕事」――そうした雑多な業務に柔軟に対応するのが私たちの役割です。
具体的には、緑地管理、郵便物の仕分け・配達、現場の修繕補助や一次対応なども行っています。これは外注に頼るのではなく、社内で人員を組み、可能な限り自分たちで対応するというスタイルをとっているからこそできることです。
一般的なビルメンテナンス会社のように、「清掃だけ」や「警備だけ」といった分業型ではなく、「現場の困りごとをまるごと引き受ける」ことに価値を感じていただいています。
―――社長として働いていてご苦労されていることはありますか?
金井 品質を維持することは、私たちのような現場型の会社にとって最も重要であり、同時に最も難しい課題です。特に人手に頼る部分が大きい業界であるため、「人材の入れ替わり」や「定着のしづらさ」は常に悩みの種となっています。
現場で作業してくれる方の多くは高齢者であり、若い人材はなかなか入ってきません。たとえ若手が入社しても、業務の性質上ルールが多く、地味な作業も多いため、なかなか定着しづらいのが実情です。
また、業界全体としての課題も感じています。たとえば、大手と中小企業とでは、現場作業員の給与に大きな差があるケースも少なくありません。現場で真面目に働く人が生活に困るような水準では、当然ながら長く働いてもらうことは難しいでしょう。
私自身、他社の管理職の方々と話す中で、「この給与じゃ生活できないよね」「それじゃ辞めるのも無理はない」といった声を聞くことがあり、非常に共感しています。では、どうすればこの業界で“差別化”を図れるのか――それが今、最も頭を悩ませている課題です。
現場業務の単価には限界があるため、大きな給与差をつけることは現実的には難しい。その中で、どうにか「働きやすさ」や「安心感」、あるいは「やりがい」など、金銭以外の価値を生み出すことができないかと、模索を続けています。
そして、最終的に会社として最も大切なのは「継続すること」だと考えています。利益を上げることももちろん重要ですが、それはあくまで会社が継続するための手段にすぎません。
―――会社の継続に向けて取り組んでいることはありますか?
金井 現場作業の単価にはどうしても限界があり、特に中小企業では、給与面で大手と大きな差をつけることが難しいのが現実です。そうした中で、「どうすれば人が定着するか」「どうすればやりがいや成長を実感できるか」を常に考えながら取り組んでいます。
数年前、「このままでは本当に差別化ができなくなる」と危機感を覚え、ビルクリーニング技能士などの資格手当を見直し、増額しました。すると、それをきっかけに若手社員の中にも資格取得に前向きな人が増え、少しずつ良い変化が現れ始めました。
今の若い世代が、ライフステージが変化しても安定して働き続けられるようにするには、会社側がその土台をしっかり整えておく必要があると考えています。その取り組みの一つとして、資格取得の支援に本格的に力を入れ始めました。
たとえば、ビルクリーニング技能士の実技練習ができる専用スペースを社内に新たに整備し、業務の合間に練習できる環境を整えました。また、自分自身も講習に関わり、内容を理解したうえで、受検者をサポートする体制を作っています。
―――神奈川県協会でビルクリーニング技能検定の講師もされていますね。
金井 ビルクリーニング技能検定に関わるようになって、もう6〜7年になります。最初のきっかけは、オーエルサービスの山本領矢さん(参考リンク:https://www.j-bma.or.jp/hope/87566)の存在でした。講習会で指導されている姿を見て、「この人と仲良くなりたい」と思ったことが、関わり始めた原点です。
その後、神奈川県ビルメンテナンス協会の皆さまにもよくしていただき、さまざまな学びや経験を得ることができました。
現在では、講習などを通じて自分が学んだ知識や技術を、自社の現場や従業員にもフィードバックできるようになり、少しずつ還元できていると感じています。


―――障がい者雇用やアビリンピックへの取り組みも携わっているんですね?
金井 我々の業界では、障がいのある方が一定数いることは自然なことだと考えています。障害者手帳を持っていないものの、実質的に障がいがあるとみなされる方や、症状によっては明らかに障がいに該当しても手帳が発行されない病気の方も存在します。精神的な不調や人工透析などの影響で、誰もが将来的に障がい者になる可能性があると考えると、「障がい者」という括りで分けるよりも、様々な方が働ける環境を整えることが重要だと感じています。
私自身、身近に障がいのある方がおり、働きたくても働ける場所が少ない現状に問題を感じていました。その方の家族が自立を望む気持ちを理解し、支援したいと思い関わり始めました。現場作業だけでなく、事務作業など多様な業務ができる障がい者の方もいるため、多様な働き方に対応できる環境整備が不可欠だと考えています。
実際にオフィスでは、バリアフリー設備(リフト、多目的トイレ、車椅子対応など)を導入し、障がいのある方も働きやすい環境づくりに努めています。以前には、足の不自由な方が勤務していた実績もあります。
障がい者か健常者かで区別するのではなく、「労働力」としてフラットに捉え、その方が持つ能力を最大限発揮できる環境を整えることが大切だと考えています。


―――今後のビルメンテナンスの仕事にどのような可能性があると感じていますか?
金井 ビルメンテナンスの仕事は、今後AIやロボットが進化しても、完全に人の手に取って代わることはないと考えています。だからこそ、これからの時代においても人の力が必要とされ続けるこの業界には、大きな可能性を感じています。
現時点では、実用面でロボット活用に限界があると感じています。例えば、清掃ロボットは床掃除には使えますが、当社のようにクリーンルームや壁・天井の清掃が求められる現場では、依然として人の手による対応が不可欠です。
特に当社では清掃と同時に虫の発生リスク管理も行っており、虫の餌となるものや潜む場所を特定して対応する必要があります。こうした判断や対応は、現段階のロボット技術ではまだ難しいと感じています。
最新技術は展示会などで常にチェックしていますが、現状では自社の基準を満たすロボットはまだ登場しておらず、今もなお人の手による業務が中心であるのが現実です。
―――業務におけるAIの活用はいかがですか?
金井 現在、総務や管理部門の人材が不足している状況を踏まえ、AIを活用して業務効率化を進めています。具体的には、契約書の内容を精査する法務系のAIツールを導入し、人手不足を補っています。
また、従業員のメンタルヘルスやチーム適性の把握に向けて、AIを使ったウェルビーイング支援ツールも取り入れています。これには性格診断や月ごとのメンタルチェック機能があり、早期の不調発見が可能です。さらに、新規採用者が既存チームに適合するかどうかの分析にも活用しています。
これらの取り組みは、従業員満足度の向上や離職防止に効果を上げており、今後も不足部分については積極的にAI導入を検討していく方針です。ただし、「何にどこまでAIを活用するか」という見極めは重要であり、慎重に検討を重ねながら進めています。
Corporate Information
- 昌永産業 株式会社
- 〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内180番地
- TEL: 0465-36-2706
- 代表取締役社長 金井 晃海 HP: https://www.shoei.co.jp/