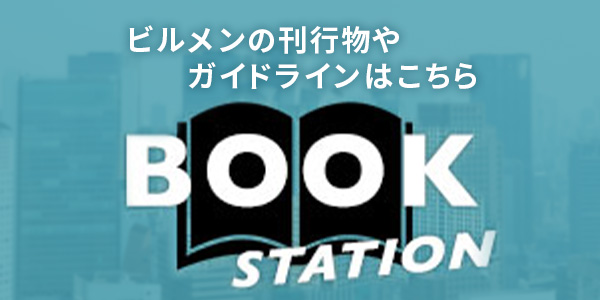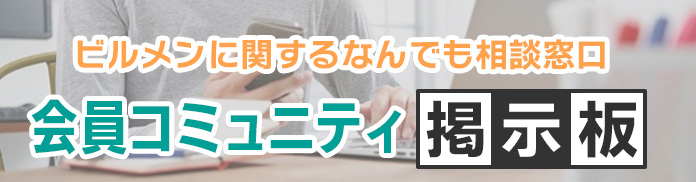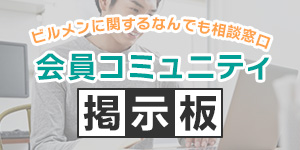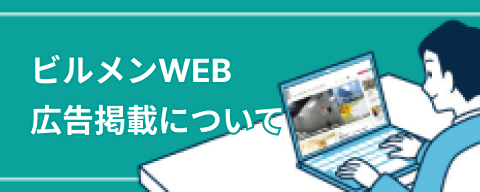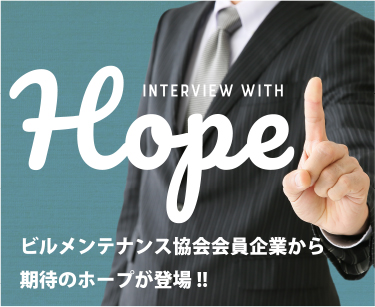
FILE 088
株式会社冨永産業
代表取締役社長 冨永 大輔 氏

―――株式会社冨永産業について教えてください。冨永さんは子どもの頃からビルメンテナンス業界で働くと思ってましたか?
冨永 当社は1965年にビルメンテナンス会社として創業し、2002年に私が二代目として父の後を継ぎました。
小さい頃から、身近にビルメンテナンスの仕事があるのが当たり前の環境で育ったんです。だから「必ず父の後を継ぐぞ」という強い決意があったわけではなく、自然な流れでこの仕事を選んだ、という感じですね。
学生時代も、休みの日は実家でアルバイトをして清掃の仕事を手伝っていました。その経験が、現場での知識や技術、従業員とのコミュニケーションの基礎になっていると感じます。
―――社長に就任したとき、苦労したことはありましたか?
冨永 大学進学をきっかけに大阪に出て、卒業後もしばらくは大阪のビルメンテナンス会社で働き、知識や技術を身につけました。ところが、大分に戻って会社を継ぐことになったときに気づいたのが、大阪と大分では建物の規模がまったく違うということ。大阪で学んだことをそのまま活かすのは難しく、その点は正直苦労しましたね。
ただ、学生時代のアルバイトでの経験があったおかげで、清掃用具の扱いや従業員とのやり取りには問題なく対応できたのかなと考えています。
また、現場に足を運んで従業員の様子を見たり、オーナーと直接話をしたりしていたんですが、社長に就任して間もなくリーマンショックが起きまして…。現場に顔を出すと「値下げしてほしい」と言われてしまい、なかなか気軽に現場へ行けなくなった時期があり、それは大変でしたね。
―――今後、冨永産業をどんな会社にしていきたいですか?
冨永 当社は地域に根ざした会社ですので、これからも長くお付き合いのあるお客さまからのご依頼を一つひとつ大切にしていきたいと思っています。
また、従業員の皆さんには「ちょっとした気配り」を常に意識してほしいですね。お客さまから「ありがとう」と言っていただける仕事ができれば、自分たちも気持ちよく働けますし、その積み重ねが信頼につながります。 そして「冨永産業は気配りが行き届いているから、またお願いしたい」と思っていただけるような会社であり続けたいと思っています。
教育現場との出会いから始まった障がい者支援
―――ところで、冨永さんが会長を務められている大分県ビルメンテナンス協会では、障がい者支援事業に力を入れていると伺いました。何かきっかけがあったのでしょうか?
冨永 大分県教育委員会の教育長から「アビリンピックを参考に、就労支援を目的とした特別支援学校の高校生向けの検定をつくりたい。協力してもらえませんか」というお話をいただいたのがきっかけです。
検定の名前は「大分県特別支援学校メンテナンス技能検定(チャレンジ検定)」といいます。
実は、私は以前に大分県PTA連合会の会長をしていて、その関係で教育委員会に出入りすることが多かったんです。
そんな折、アビリンピックに注目していた大分県教育長の耳に「PTA連合会の会長はビルメンテナンス業界の人らしい」という情報が入ったようで…(笑)。私が教育委員会に顔を出すタイミングを見計らって声をかけてくださったんですね。
そうしたご縁があって、大分県協会として「チャレンジ検定」に協力するようになりました。
―――「チャレンジ検定」について、詳しく教えていただけますか?
冨永 「チャレンジ検定」は、大分県教育委員会が実施する特別支援学校での作業学習などを通じて身につけた清掃に関する知識や技能、そして態度を評価する検定です。
大分県協会では、約10年前から講師を派遣して取り組んでいます。検定対策だけでなく、清掃用具の使い方や、実際に社会に出て働くことを意識した指導も行っているんです。
今も年に2回ほど、県内各地の特別支援学校に講師が出向いて授業をしています。
2021年4月には「大分県立さくらの杜高等支援学校」が開校しましたが、このチャレンジ検定が評価され、同校の中に清掃の仕事に特化した「クリーンコース」が設けられたんです。
この学校は、知的障がいのある方を対象に、一般就労を促進することを目的とした高等特別支援学校です。
現在も協会から講師を派遣し、現場で即戦力になれるよう清掃技術を教えています。
そして今年、初めての卒業生を送り出すことができました。こうした取り組みは全国的に見ても珍しいのではないかと思います。


―――「チャレンジ検定」や「大分県立さくらの杜高等支援学校の開校」を通じて、どんな成果や変化がありましたか?
冨永 生徒さんたちにとって一番大きいのは、自分の努力が“検定”という形で評価されることだと思います。単に授業で学ぶだけでなく、「自分は清掃の技術を身につけている」「社会で役立てるんだ」という自信につながっているように感じます。
また、保護者の方からも「働くことを具体的にイメージできるようになった」という声をいただいていて、私たちにとっても大きな励みになっています。
そして何より嬉しいのは、卒業生が実際にビルメンテナンス業界に就職し、現場で活躍してくれることです。彼らが社会人として一歩を踏み出し、その姿を後輩たちが見て「自分も頑張ろう」と思えるようになれば、この取り組みがさらに広がっていくのではないかと期待しています。
―――今後さらにこのような取り組みが広がり、卒業生が増えていくといいですね。
冨永 はい。今年は一期生として2名が卒業し、2名とも大分県協会の会員企業に就職しました。
現在の3年生は、通常1クラス8名編成のところ、「クリーンコース」は評判が良く、2クラス16名が在籍しています。
大分県も少子高齢化の影響が大きいですから、こうして若い力が卒業生として会員企業に入ることは、とても大きな意味があります。
この取り組みを10年、20年と続けていくことで、ビルメンテナンス業界にどんどん若い力が入って業界全体が活性化していくのを楽しみにしています。
―――業界内外にビルメンテナンスという仕事の魅力を、どのように伝えていきたいですか?
冨永 支援学校の生徒さんには、いつもこう伝えています。
「ビルメンテナンスはただのお掃除ではなく、建物を手入れする仕事です。手入れをすることで建物の寿命を延ばしたり、資産価値を上げたりすることができるんだよ。みんなが生まれたときからある建物が今も綺麗で清潔なのは、ビルメンテナンスという職業があるからなんだよ」と。
業界で働く方々には、ぜひ「自分たちが建物を清潔に保っているからこそ、人々が安心して利用できる」ということを意識してほしいですね。
たとえ同じ作業の繰り返しであっても、その積み重ねが誰かの安心につながっていると思えば、日々の仕事により大きなやりがいを感じられるのではないかと思います。
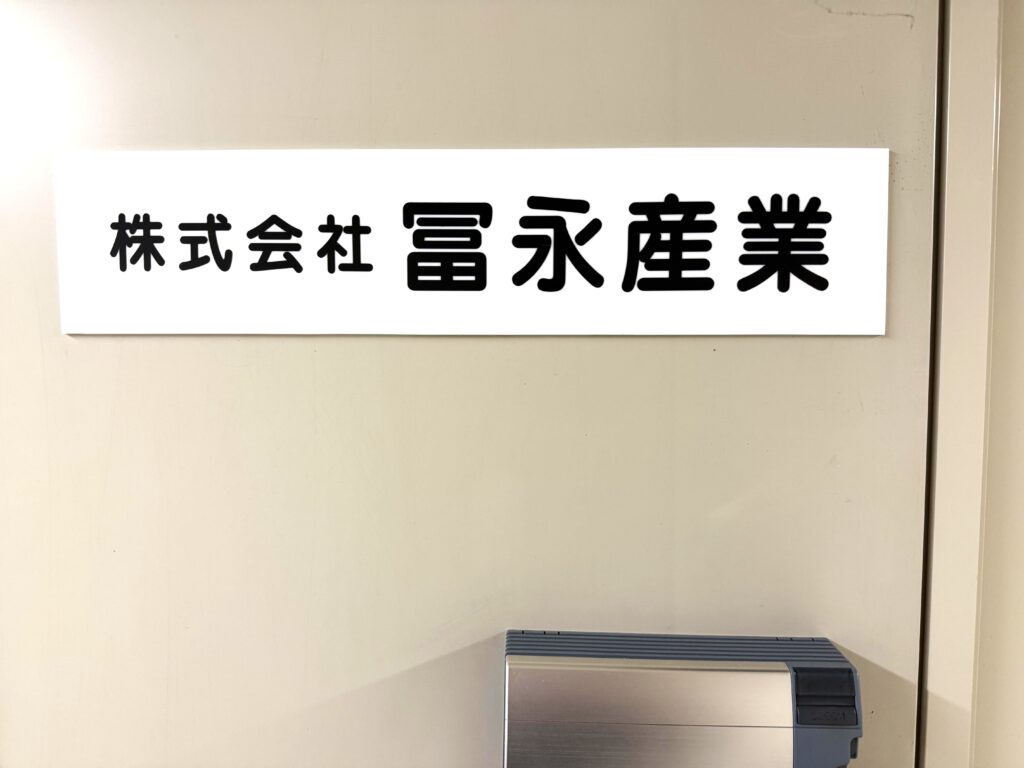
Corporate Information
- 株式会社冨永産業
- 〒870-0034 大分県大分市都町1丁目3−2 大分都町ビル7階
- 代表取締役社長 冨永 大輔