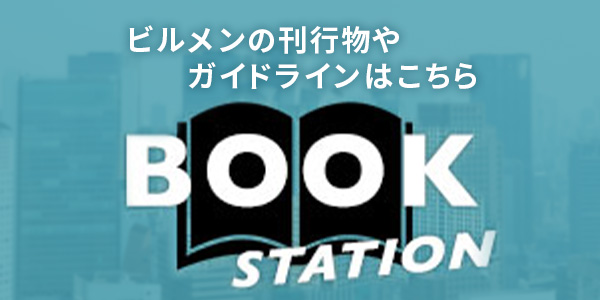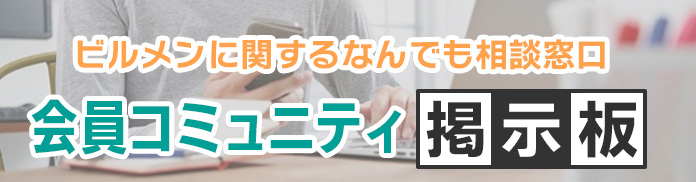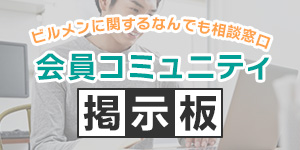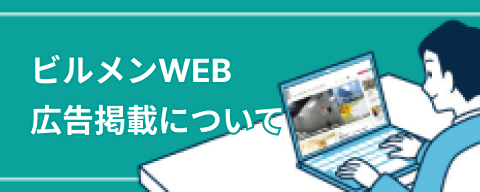価格転嫁7つの心得と15のテクニック講座 第4回
みなさんこんにちは。中小企業診断士の初鹿野浩明(はつかの ひろあき)と申します。今回で第4回目になります。
第2回、第3回では、価格転嫁の7つの心得のお話をさせていただきました。「品質を落とさない」「廃業するよりも値上げ」「ターゲットを変える・増やす」「付加価値を上げる」「周りの動きに合わせる」「少しずつ上げる」「額でなくパーセントで考える」という内容でした。
今回からは、実際に値上げをするためのテクニックとして前編、中編、後編に分け、15の例を挙げていきます。
価格転嫁15のテクニック(前編)
物価高が続いている中で、実際に自店・自社の価格を上げようとすると様々な葛藤が生じます。多くの中小企業・小規模事業者では、悩んで悩んで値上げのチャンスを逃します。その結果、わずかしか値上げができなかったという事例を数多く見ます。
実際に周りの事業者ではどのように値上げをしているのかというのを15パターンほど書き出してみました。BtoC(対消費者向け)とBtoB(対企業向け)では若干異なりますが、共通することも多々あります。さらに、下請性が強い中小企業企業の場合は、自ら価格改定が難しいという課題もあります。そのような中で、前述した7つの心得も参考にし、それぞれの事業者にあった取組をしてください。
【価格転嫁 テクニック その1】 とりあえず値上げ
言わずと知れた、「値札の張替」です。お詫び型とツッパリ型があります。
「お詫び型」は、「料金改定のお知らせ(お願い)」といった張り紙や手紙を書いてお客様に値上げを伝える手法です。値上げの理由を示しながらお詫びして、何月何日から値上げすることを伝えます。
対して「ツッパリ型」は、問答無用に値札を張り替えます。メニューを書き換えたり、商品棚の値札を入れ替えたりといた手法です。
いずれにしろ、注意しておきたいことは、メニューブックや値札の一部を書き替えるだけではなく、できれば、メニューブックや値札を刷新したほうがいいです。見た目がキレイなだけではなく、後々まで価格を改定したことがお客様にわかり、良い印象を与えません。

【価格転嫁 テクニック その2】減量法
材料費が上がった時によく見かける手法です。材料費が上がった分だけ、内容量を減らすという手法です。コンビニのおにぎりや、バターの量が極端に減ったことが記憶に新しいです。
デフレ経済の時はよく見かけましたが、インフレとなった現在ではあまり有効とは言えません。インフレの時は材料費だけが上がるのではく、それ以外の経費も上がるので実質的な経費削減にはなりません。

【価格転嫁 テクニック その3】増量法
商品の内容量を増やして、価格も上げるという手法です。極端に言えば、内容量を3倍にして価格も3倍にします。インフレが進む中でこの手法が増えてきました。デフレ経済の時には、増量した時は数量割引といって安くしていましたが、インフレ経済の時には単位当たりの単価を下げることはありません。単位当たりの価格は同じであることが基本です。
このような手法はインフレ経済の時には有効です。狭い意味で販売の「規模の経済性」が成り立っているからです(一度の手間で沢山販売できる手法)。しかしながら、「減量法よりは良いが、充分とは言い難い」と感じています。当然ですが、値上げの方が効果はあります。

【価格転嫁 テクニック その4】段階法
価格転嫁7つの心得のページでも話ましたが、一度に上げないで、少しずつ数回に分けるという手法です。
何らかの理由で、材料や経費の高騰に対応できず、価格転嫁に出遅れた場合に有効です。一度に20%とか30%と値上げをすると、お客様が驚いて急激な買い控えの体制を取ってしまいがちになります。それらの消費者行動を避けるために少しずつ値上げをするようにしましょう。
著者の経験則ですが、一度に値段を上げるのは、10%くらいが限界かと思っています。目標値上げが20%以上の時は、少なくとも2回~3回以上に分けて値上げをしましょう。また、一度値上げをしたら、3ヶ月~6ヶ月くらいの間は我慢をするように心がけてください。また、目標とする最終価格も把握しておくことが特に重要です。

【価格転嫁 テクニック その5】入替法
安い商品を望むお客様もいますが、顧客嗜好の2極化が進む中では、より良いものを望む人も数多く存在します。より良い類似品と入れ替えるという方法もあります。
100円ショップの商品は著者も使っていますが、道具として使う場合、シチュエーション毎に使い分けています。このように、より安い品揃えという概念から、より良い品揃えという概念も重要かと思います。
長く続いたデフレ経済の中で、中小企業・小規模事業者の中には「お客様は安いものを望んでいる」と思ってしまっている人も多くいます。高級ブランド品という意味ではありませんが、「より良いものを適切な価格で販売する」という視点も忘れないでください。
以上で価格転嫁15のテクニック(前編)として5つのパターンをご紹介しました。次回は中編として、さらに5つのパターンをご紹介します。
◆◇◆
【本記事は連載の第4回です。これまでの回もあわせてご覧ください】
■第3回「価格転嫁7つの心得(後編)」
■第2回「価格転嫁7つの心得(前編)」
■第1回「物価高の現状」
株式会社経営科学研究所 代表取締役
中小企業診断士