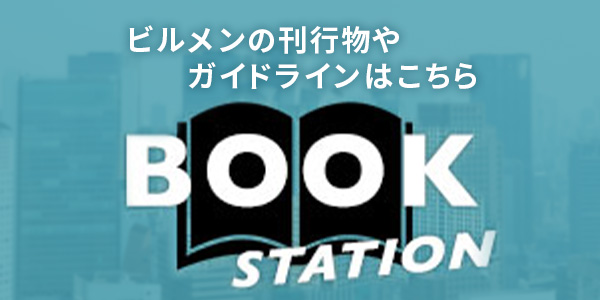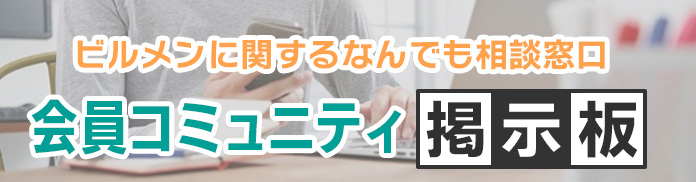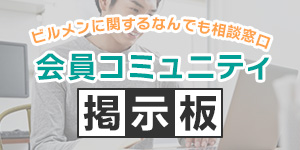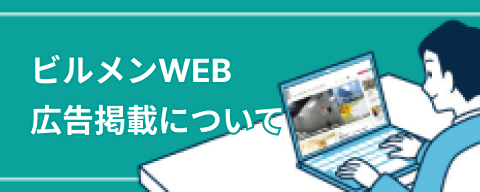価格転嫁7つの心得と15のテクニック講座 第3回
みなさんこんにちは。中小企業診断士の初鹿野浩明(はつかの ひろあき)と申します。今回で第3回目になります。
前回は、価格転嫁の心得として、「品質を落とさない」「廃業するよりも値上げ」「ターゲットを変える・増やす」というお話をしました。第3回目では、価格転嫁を図る場合の心得(後編)についてお話をしたいと思います。
価格転嫁7つの心得(後編)
【価格転嫁 心得の4】付加価値を上げる
より良いものを売る。価格の高いもの、利益額がとれ、それでもお客様が納得して買ってもらえる商品・サービスを提供するという考え方も重要です。
そのためには、大手や近隣同業他社と価格競争をするのではなく、自社の特徴・強み・オリジナリティーを活かした商品展開・商品開発をすることです。商品やサービスに相応の価値が認められれば、その業界では独壇場の働きをすることができます。
過去30年に渡るデフレ下において、日本の産業は、効率化、省人化を目指してきました。そのため、「薄利多売」が最も重要とされ、利益を深くすることを悪いことのような考え方になってきました。
そのため、新しい価値を創造するということよりも、どうやって経費を削減しようか?という考え方が主流になってきています。
効率化を進めることも大切なことですが、もう一度、創造性とはなにかという考え方も大切にしてください。

【価格転嫁 心得の5】周りの動きに合わせる
周りの価格転嫁に追随して値段を上げるというのが一般消費者からの納得も高く好ましいようです。通常、4月か10月に大手企業が価格を上げることをTVなどの情報で流します。これらの時が価格転嫁(値上げ)のチャンスです。
デフレ禍では、事業者の仕入価格が上がることに関して、一般消費者は知らない場合がほとんどでした。ところが近年では商品の価格が上がることをマスコミなどで大きく取り上げられ報道されるようになっています。一般消費者も価格が上がることは容易に想像できます。
以前、よく見られた手法では、値上がりする前に余分に仕入れたりすることで、値段を上げることを回避してきました。仕入れ業者から値上げの情報があり、3ヶ月分とか半年分を余分に仕入れて値上げを回避するというのがデフレ経済禍の対策の一つでした。
ところが、インフレ経済禍には、また、半年後に価格が上昇する可能性があります。この時に値上げ怠った場合、値上げのタイミングを逸してしまう場合があります。
自社の利益が行き詰ってから値段を上げると、お客様や消費者にとっては唐突に値段が上がった感があり不満が出やすくなます。そのため、お客様が急激に減るという現象が起こる場合もあります。
しかし、大手企業が値上げを提示した時と同時に値段を上げることは、消費者からみれば十分に納得性・説得性があります。

【価格転嫁 心得の6】少しずつ上げる
仕入れや経費が高くなっても販売価格に転嫁できず、我慢して、我慢して、我慢しきれなくなって一度に沢山上げると、お客様はびっくりします。場合によっては、売上が急激に低下する場合もあります。少しずつ回数を重ねて値上げをするようにしましょう。
著者の経験上の目安ですが、一度に上げるのは、10%以内が目安です。業種にもよると思います。20%以上の価格転嫁を実行する場合は、2,3回以上に分けてあげるようにしましょう。一度値上げをしたら、2回目以降の値上げは3ヶ月~6ヶ月程度の期間を置きましょう。
2年間で5回に分けて、20%以上値上げをした企業もあります。

【価格転嫁 心得の7】額ではなくパーセントで考える
デフレ経済禍では、材料費が上がった時、その上昇した金額分だけを自社の価格に転嫁するというパターンありました。
例えば、売価1,000円、材料費300円(材料費率30%)、さらに、経費や人件費60%、利益10%の製品を作っていたとします。
材料費が1.5倍の450円になった時、デフレ経済禍の時には、材料費の値上がり分の150円を上乗せした1,150円を売価として販売しました。このころは、他の経費などは変化しないので、基準となる費用(この場合は材料費)だけに目を向ければよかったのです。材料費が1.5倍(50%アップ)したにも関わらず売価を20%アップすると、今までよりも利益が増えたという現象がありました。

インフレの時は、材料だけが上がるのではありません。物価全体が同じような比率で上昇するのです。材料費に目が行くことが多いですが、一般的には、人件費の割合に同期するといわれています。
一つの基準の費用(材料費など)の「額」で考えるのではなく、割合で考えるようにしてください。材料費が30%上がったら、売価も30%上げた方が「よさそうだ」と考えてください。
以上が価格転嫁の7つの心得になります。前編の合わせてみていただけると幸いです。次回は、この7つの心得を踏まえながら、どうやって値段を上げようか?という値上げをするための15のテクニック(値上げの手法)のお話をしていきます。
◆◇◆
【本記事は連載の第3回です。これまでの回もあわせてご覧ください】
■第2回「価格転嫁7つの心得(前編)」
■第1回「物価高の現状」
株式会社経営科学研究所 代表取締役
中小企業診断士